「この内申、公立中ならもっと高くついていたんじゃないかな、、」
私立中に通う娘の通知表を見ると、そんなことを感じてしまいます。
決して、すべてのテストで高得点が取れているわけではありません。
でも、公立中で娘の学校と同じテストをしたら、平均点はたぶん各教科10〜15点くらいは下がるはず。
その中で娘が取っている点数なら、評価はもう1段階上でもおかしくないのでは?
実際、塾の模試ではそれなりの偏差値が出ていて、志望校も手が届く範囲。
塾の先生にも面談で「この程度模試で取れていれば、公立なら4や5がついていると思いますよ」と言われたことも。
中高一貫の私立なら、内申は気にしなくてもいい。
でも、うちは中高一貫ではなく、ほとんどの子が高校受験する学校です。
だからこそ、この「内申の評価のされ方」は、進路に直結してきます。
今回は、そんな「私立中で内申が取りづらい現実」と、
それが高校受験にどう響くのか――
わが家の体験を通して、正直に書いてみようと思います。
なぜ内申が取れない?
まず、”娘の中学の定期テストを公立で実施したらどうなるか?”という話から。
娘の学校の定期テストの平均点は大体5教科で300点台前半のことが多いです。
一方、地元の公立では、大体200点台後半が一般的です。
もし、娘の中学のテストを公立中で実施したら、恐らく平均点は200点台前半くらいになるのでは、と思います。
つまり、同じテストでも、平均点に100点の差が出ることになる。
それだけ学力層が違う中で、仮に娘が「平均より少し上」の点数を取ったとしても、校内の評価では、それが”中の中”くらいとなってしまうのが現実です。
今は「絶対評価」であるはずです。
でも、実際には学年内での相対的な位置を見て評価されているように感じます。
実感としては、「平均点+10点」くらいでようやく「4」がつく教科が多く、平均点では「3」が妥当とされてしまう雰囲気があります。もちろん、教科担任の裁量によって差もありますが・・・
これでは、同じ学力でも、公立中なら4,私立中では3という評価になりかねません。
実はこれ、公立でも「文教地区」と呼ばれるような、学力水準が高い学区では同じような現象が起きていて、そのような地区のお子さんたちが中学受験に流れる要因になっている、と聞いたことがあります。
実際はどうなの?娘の内申の推移と感じたこと
内申については、担任に直接聞いたことはありません。でも、通知表を見るたび、「これは上がった」「これは納得いかない」と親子でいろいろ感じできました。
数学と英語は上昇
まず、数学と英語は、中2以降で少しずつ内申が上がってきました。
・数学は中2の夏休みから個別指導を追加し、予習をしてから学校の授業に臨むようになったこと
・英語も中2の夏休みからはじめた、学研kiminiでの積み重ねが効果を発揮
正直言うと、この2教科については、教科担任との相性も影響が大きかったように思います(英、数は教科担任がそのまま3年に持ち上がり、正直ホッとしました)。
実技教科は・・・?
実技教科では、体育が「3」から「4」に上がりましたが、正直よくわかりません。というのも、娘は学内では運動神経がいいほうです(運動神経に関しては学力と逆で、公立より悪い子が多めです)。
それなのに、中1の時はまさかの「3」。むしろその時の評価が謎でした。
しかも、学年で断トツ運動神経いい子ですら「4」らしいのです。
さらには、1年の時は「3」だったのに、2年で急に「5」に上がった子も・・・ 評価基準が全く分かりません。
音楽は、筆記テストがよかったおかげで評価が上がったようです。
ただし、うちの学校の音楽のテスト、これがかなり難しいです。
実技教科なのに、とても細かい問題を出してきて、「え?これ何目指してるの?」と突っ込みたくなるレベル。娘は保育園からピアノを続けてきたので、音楽についてはそれでかなり救われている部分があります。しかし、娘の学校はピアノなどを習っている子の比率が高いため、特段有利ということはないです(その分、習っていない子は不利になってしまいます)。
筆記テストの難易度については、音楽に限らず、実技教科全般にいえること。
正直、”実技”というより”筆記で勝負”の世界になっている気も・・・
塾の先生の一言に、モヤ・・・
塾の面談で内申の話をしていたとき、先生がポロっと言ったのが、
「内部進学、させたいんじゃないですかね?」
うちは高校も併設されている私立中ですが、実際にはほとんどの生徒が外部受験をします。というのも、あまり評判がいい学校ではないからです。
でも、先生のその一言が少し引っ掛かりました。
確かに、外に出てほしくないという思いがどこかにあるかもしれない。
そんなふうに邪推してしまいたくなるくらい、内申の評価には腑に落ちない点が多いのです。
評価の矛盾と”割を食う子たち”
うちの学校、実際に「5」がつく子ももちろんいます。中には「オール5」や、それに近い子も。
でも、ふと思うのです。
この子達、公立中にいたら”オール6”も夢じゃないよね?と(もちろん”5”が上限なので、ありえないことですが)。
要は「5」がつく子はどこでもつく。でも、割を食うのは「4」や「3」をつけられている子たちなんじゃないか、と。
例えば、「4」がついていても、実力としては公立中なら「5」が妥当な子かもしれない。「3」の子も、実際は平均以上の実力があるのに、周りとの比較で評価が下がってしまっている可能性があります。
さらにややこしいのは、学校のスタンスがよくわからないこと。
中学入試説明会では、
「当校は、(県内公立トップ校)への進学率が、県内の中学でトップです!」
とアピールするのです(ちなみに中高一貫でない私立中は、県内では娘の学校のみなのである意味それは当然であり、さほど自慢するようなことでもないです・・・)。
それなのに、いざ入ってみると、内申がシビアで、むしろ足を引っ張られているような感覚になる。
一方で塾の先生は「内部進学させたいんじゃないですか?」と言うし、
「この学校は生徒たちに”本人の希望する学校”に進学してほしいのか、引き止めたいのか、どっちなの・・・?」と思う場面がたびたびあります。
正直いえば、「子供たちの希望や、将来のことを親身になって考えてほしい」ですし、「学校」とは本来そうあるべきではないでしょうか。
子供たちの努力が、評価の”構造”によって正当に報われない__
それが、内申のつけ方に対してずっと感じている違和感の正体かもしれません。
次回の記事では、実際に内申がどんな風に高校受験に影響してくるのか、そして我が家がどのように進路を考えているか、について書いてみようと思います。
🎀ここからはおすすめアイテム紹介🎀
娘の部屋にずっと掛け時計がなく・・・ ようやく購入しました。揺れるスヌーピーがとてもかわいい❤️ 小さめで、6畳の娘の部屋にはぴったり!
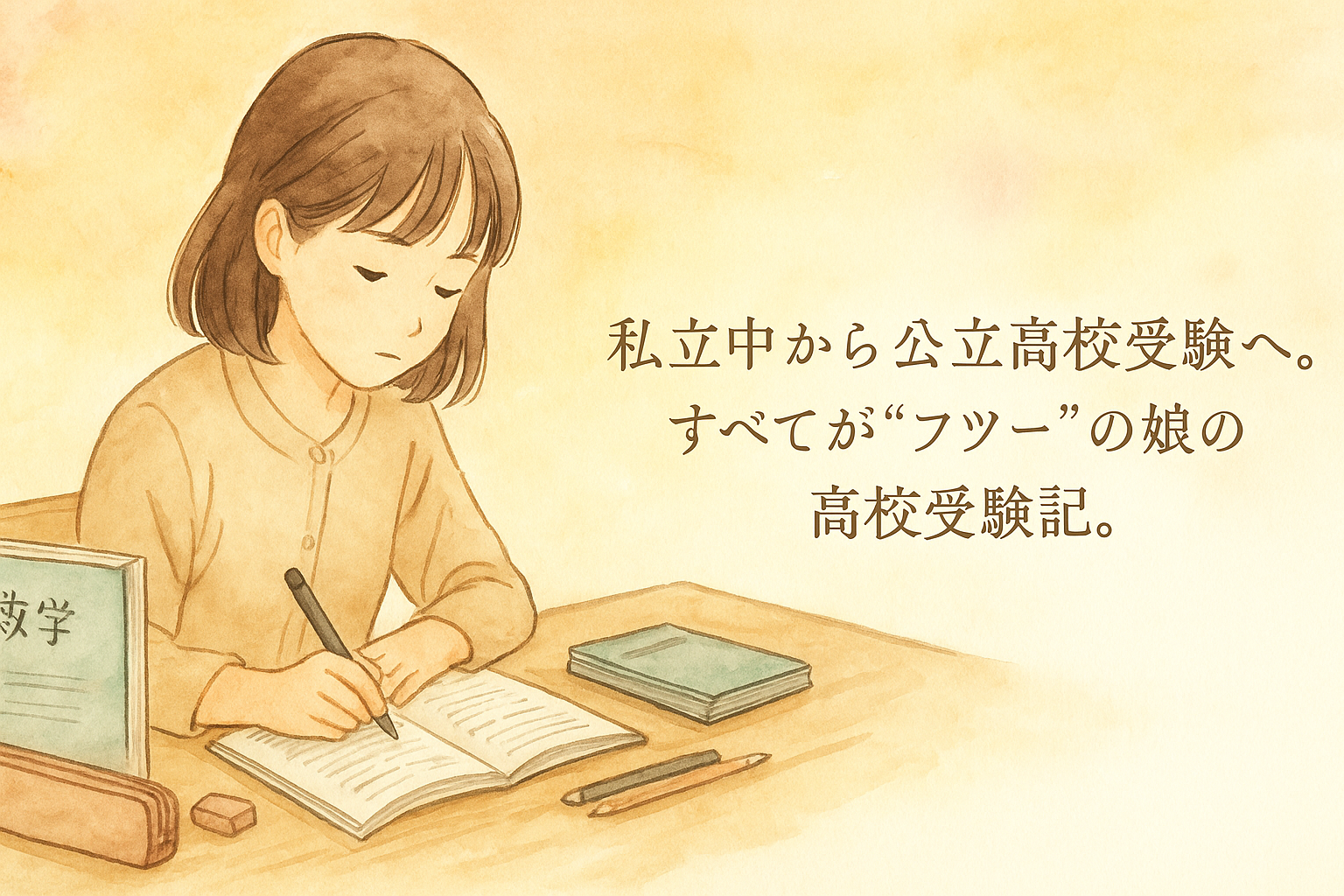


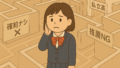
コメント